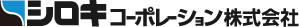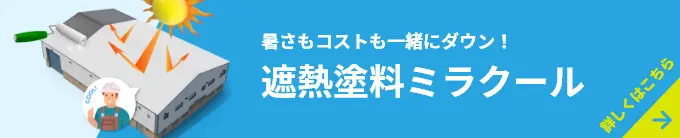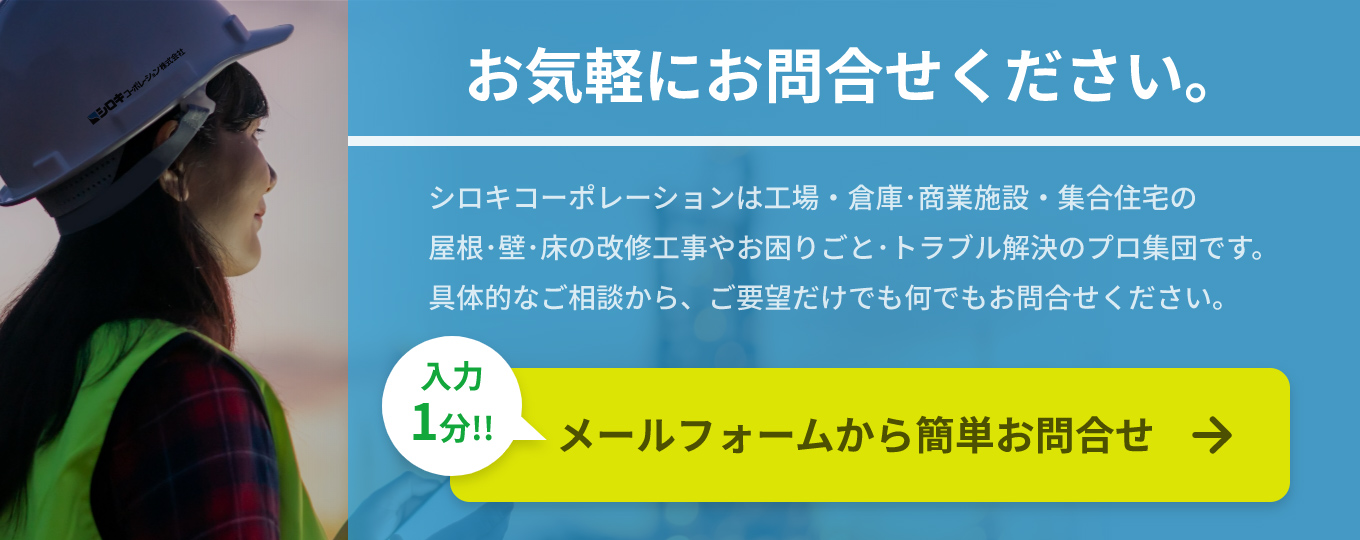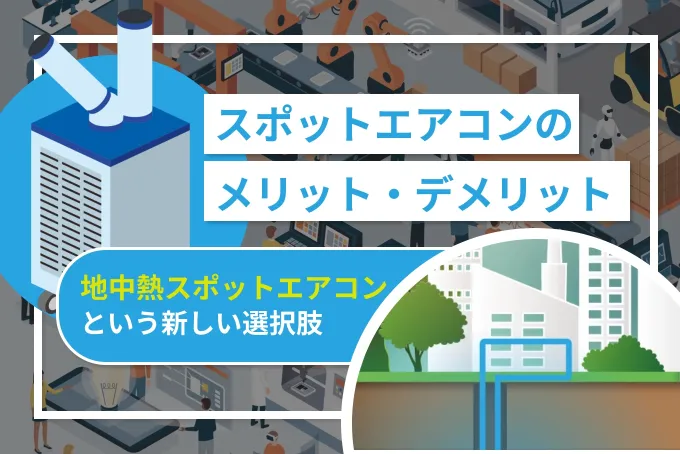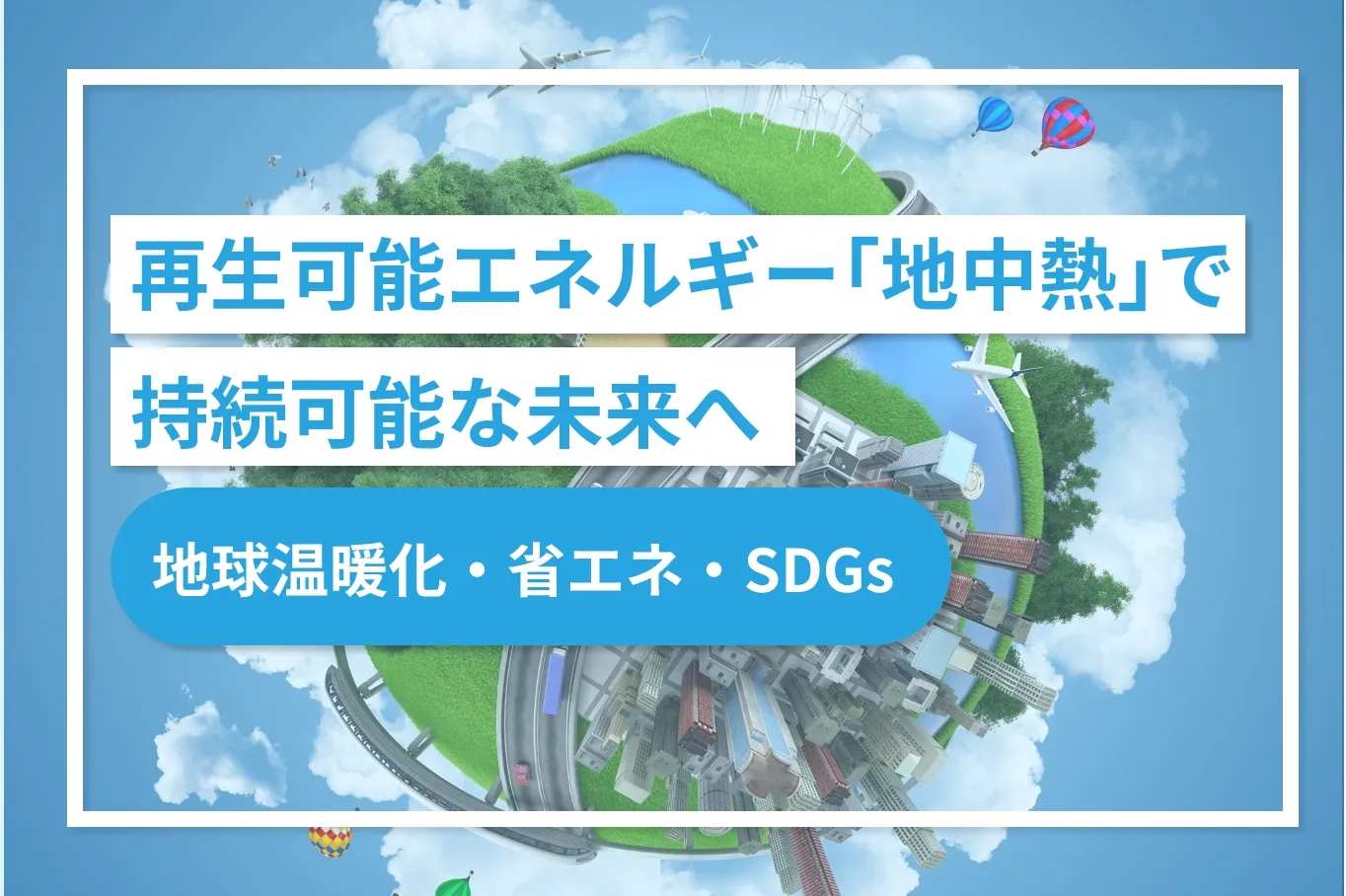【2025年最新】カーボン・クレジット、いまどうなっている?~自社で進められる排出削減方法も紹介~
この記事のリンクをコピーしました。
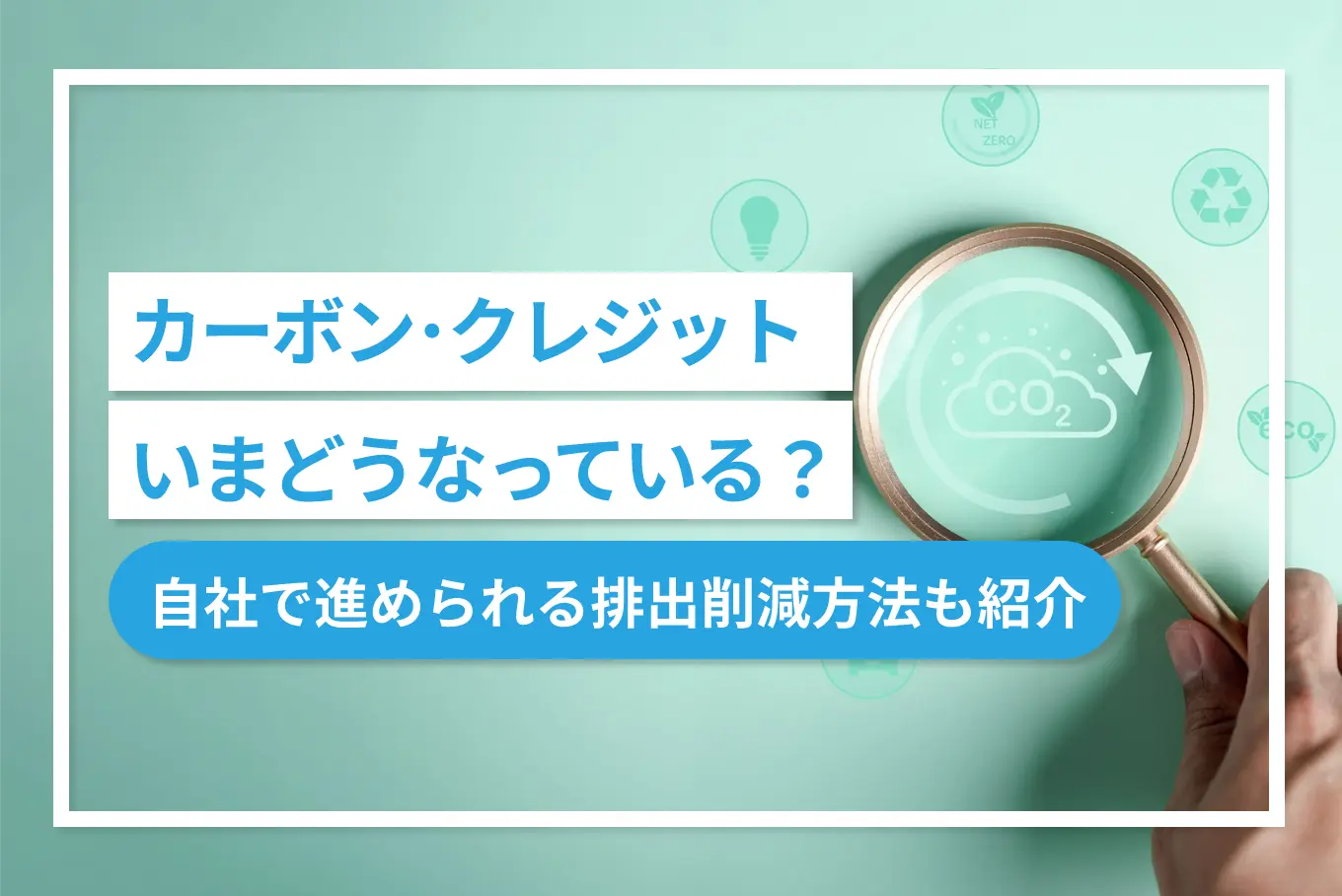
<この記事の要点>
- 企業の脱炭素経営を左右するカーボンクレジットの最新動向
- 2026年に始まる排出量取引制度(GX-ETS)の概要と企業への影響
- いま注目されるクレジット活用と自社削減策の両立戦略
- 設備投資を支援するグリーン融資の活用ポイント
- 冷房コストもCO₂も削減できる遮熱塗料の可能性
2005年、京都議定書の発効をきっかけに、温室効果ガス削減が世界基準で義務化されました。
現在は、国内外でさまざまな対策が検討されていますが、その中で注目されている取り組みの一つが「カーボン・クレジット」です。
日本では、2013年に「J-クレジット制度」がスタートし、2022年には東京証券取引所によるカーボン・クレジット市場の実証がはじまっています。
今回は、気候変動対策に取り組みたい企業、設備や経営の担当者向けに、カーボン・クレジットの浸透状況やグリーン融資制度の現状、J-クレジットを購入できる制度、団体などについて、くわしく解説いたします。
カーボン・クレジットとは

カーボン・クレジットは、温室効果ガスの排出量を削減する、もしくは吸収するプロジェクトを実施した際に発行される証書です。
1クレジット=1トン相当のCO₂排出削減として認証され、取引が可能です。
「温室効果ガス削減施策を講じているけれど、目標に達していない」
という場合、クレジットの購入で、未達部分の埋め合わせができます。この企業の購入行動を「CO₂オフセット」と呼びます。
カーボン・クレジットの浸透状況
カーボン・クレジット市場は、引き続き拡大傾向にあります。例えば、テスラは 2024年にカーボン・クレジット売上で約 27.6 億ドル(数千億円規模)を記録したとの報も見受けられており、企業間での排出権取引が依然として注目されています。
EUの場合、CO₂排出量の削減が目標値に達しない場合、罰金を支払うというルールがあります。罰金を支払うよりも、クレジット購入の方が経営負担を減らせる、という背景があり、カーボン・クレジットを導入している企業が少なくありません。
日本企業におけるカーボン・クレジットの購入状況

日本では、2013年にJ-クレジット制度がスタート。2022年には、東京証券取引所によるカーボン・クレジット市場の実証がはじまっています。一方で、実際に購入している、という企業はまだほんの一部、というのが現状です。
大阪商工会議所が2024年、会員企業向けに実施したアンケートでは、カーボン・クレジットの利用をしたことがあるか、という設問に対して「ある」と答えた企業が7.5%、「今はないが、将来利用が決定している」と答えた企業が2.0%となり、全体の1割に満たない結果となりました。
日本では、2026年を目処にCO₂排出量取引が、本格導入される予定になっていますが、経済産業省が「カーボン・クレジット購入の上限を諸外国の現状を参考に排出量の10%に制限する」という検討方針を打ち出している背景もあり、購入によってCO₂オフセットを実現できる量には限りがあります。
今後、10%の上限を引き下げる可能性もあり、引き続きCO₂対策への企業努力が求められています。
<参考出典>
カーボン・クレジット購入に使える制度・団体
CO₂削減のために、日本で利用できる制度・団体は「J-クレジット制度」もしくは東京証券取引所の「カーボン・クレジット市場」です。
J-クレジット制度を利用する場合、「J-クレジット・プロバイダー」に仲介してもらう、もしくは「売り出しクレジット一覧」に名前のある保有者から購入します。
どのようなクレジットが取引されているのか、購入の流れなどは、公式サイトから確認可能です。
J-クレジット制度:https://japancredit.go.jp/
東京証券取引所のカーボン・クレジット市場は、登録の要件があります。利用を検討しているなら、どのような要件があるのか、事前に確認しておくとよいでしょう。
カーボンクレジット市場(JPX):https://www.jpx.co.jp/equities/carbon-credit/index.html
前述したとおり、企業がJ-クレジットや東京証券取引所で購入できるカーボン・クレジットの量には限りがあります。上手に活用しながら、自社独自の温室効果ガス削減施策を進めていきましょう。
工場・倉庫などの建物で、温室効果ガスの削減を目指すなら、遮熱・断熱対策や設備更新などによるエネルギー効率の改善を検討すると、CO₂削減につながります。
コラム「カーボン・クレジットの価格動向と今後の見通し」
2022年に開設された、東証のカーボン・クレジット市場。はじめは1tあたり3,000円くらいの取引価格でしたが、再エネ(電力)に分類されるクレジットについては2024年6月以降、6,000円を超えるケースが出てくるなど、当初の倍近い価格をつける日がみられます。
執筆(2025年10月7日)時点では、再エネ(電力)の基準価格は5,850円となっており、引き続き当初よりも高値が続いている傾向が分かります。
また今後、2026年を目処に、CO₂排出量に関連する制度(GX-ETS)が本格的に導入される予定です。GX-ETS制度が実施されると、対象となる300~400社にCO₂排出量の上限となる枠が割り当てられる見込みです。
枠を超えて排出した場合、企業は、別の企業から余ったカーボン・クレジットを購入するか、もしくはペナルティとして金銭を支払う必要が出てくるため、カーボン・クレジット市場に、より注目が集まると予測されます。
<参考出典>
「グリーン融資」制度は活用できる?

グリーン融資(グリーンローン)は、企業や地方自治体などが、環境問題解決を目的とした取り組み(グリーンプロジェクト)を実施する際に、金融機関から融資を受けられる制度です。
再エネ設備の導入や、建物の省エネ改修や温度対策といった取り組みに活用されるケースがあり、CO₂削減に向けた施策にも活用できます。
どのような施策が融資の対象になるのか、実際の事例を参考にしながら、地域の金融機関で相談してみてください。
国内における主なグリーンローン事例(環境省):
https://greenfinanceportal.env.go.jp/loan/issuance_data/issuance_list.html
グリーンローンを活用しながら、カーボン・クレジット制度を上手に組み合わせると、より効果的な気候変動対策につながります。
グリーンファイナンスポータル(環境省):
https://greenfinanceportal.env.go.jp/loan/overview/about.html
オフセットだけに頼らない、自社で進める排出削減
カーボン・クレジットで賄えるのは、CO₂削減目標の10%程度が上限になる予定だと、先ほどお伝えしました。
つまり残りの9割は、自社でCO₂削減に取り組む必要があります。
何からはじめるべきか、施策を検討しているなら、工場、倉庫などの建物、設備向けの対策を取り入れてみるのも、有効な方法です。
太陽光パネルを屋上に設置したり、LED照明化や空調の最適化を進めたり、といった取り組みをすでに実施している企業もあります。いち早く動いている企業の事例をヒントに、自社でできそうな対策を取り入れてみてください。
遮熱塗料で冷房コストもCO₂も削減

遮熱塗料を活用した建物の省エネ対策は、温室効果ガス削減に有効な手段の一つです。
シロキコーポレーションが扱う遮熱塗料「ミラクール」は、屋根や外壁に塗布することで建物表面の温度上昇を抑え、工場や倉庫の空調効率を高めます。
室内の温度上昇を防ぐことで冷房負荷を軽減し、結果として電力消費とCO₂排出量を削減できます。
さらに、作業環境も快適になるなど、暑さ対策や労働環境の改善にも効果があります。
大規模な設備導入は難しい、CO₂削減対策に割く時間やリソースが足りていない、という場合は、負担を抑えながら取り組める環境対策を検討するとよいでしょう。
最後に
カーボン・クレジットをはじめとしたCO₂削減のための環境対策は、国内外で今後ますます重要視されると考えられます。日本でも2026年以降、一部企業にCO₂排出量の目標が設定される予定になっているなど、具体的な対策が求められています。
CO₂対策ができている企業は、社会的なイメージが良くなるという点も導入するメリットです。自社でできる方法を取り入れながら、必要に応じたカーボン・クレジットの購入も検討して、環境に配慮した企業経営を進めていきましょう。
<この記事のまとめ>
- カーボンクレジット市場の拡大により、企業の脱炭素経営が本格化している。
- 排出量取引制度(GX-ETS)は、企業に排出量の上限管理と削減努力を求める仕組みである。
- クレジット購入だけでなく、自社で省エネや排出削減に取り組むことが重要である。
- グリーン融資を活用すれば、省エネ投資を計画的に進めることができる。
- ミラクールなどの遮熱塗料を用いた対策は、負担を抑えながら省エネと快適な作業環境を実現できる。